深煎りコーヒーが脳の健康によい、らしいのです!
私、島規之は来年で44歳になってしまいます。
小学校の時から友達と話すのは、お酒の飲む量が減ったとか、お肉が沢山食べられなくなった、だとか、朝目覚める時間が早くなったとか、徹夜できなくなったとか、せやろー!なんて、そんな話で盛り上がってしまいます。
肩こりも取れにくいし、目もすこしずつ悪くなってきた。
10歳からのお付き合いのある友達とは、年齢についての話が多くなってきたこの頃です。
健康についても、少しずつ考える様になった。
整腸のために毎日ビオフェルミンを飲んだり。
心には歳を重ねて見えてくることもあるけども、身体には歳を重ねて見えにくくなるものがあるなぁ、なんて、老眼になりつつある僕が、そんなことを思ったりして、どうやら健康のことを考える歳になってきたんだなぁ、と笑いつつ。
ということで、今回は健康について。
こんにちは 焙煎アーティスト島規之です。
深煎りコーヒーが脳の健康によい、らしい
そうなんだそうです。
昨晩、寝る前にツィッターで情報チェック!と言えばかっちょよいですが、まぁその、ぶらっと見てたんですね。
友達は何したのかなぁとか、仲間は何をしたのかなぁなんて、みんなのツィートを見て、自分もやった気になったり、行った気になったり。
そこで、ですね、スクロールしていくスマホの画面に、このツィートがパッと目に付きました。
コーヒーが脳の健康によい理由が判明。ローストは深煎りの一択で|ライフハッカー[日本版] https://t.co/Wb5evtkLUD @lifehackerjapanさんから
— ゆかりん (@yukaron1) 2018年11月30日
アルツハイマーやパーキンソン病には、コーヒーが予防に役立つ可能性がある、というのは近年発表されていましたが、まだまだ研究はこれから、だと聞いておりました。
今回の情報では、一歩進んで、深煎りの方がより効果がある、ということが伝えられています。

カギはコーヒーのローストで生成されるフェニルインダン
この「フェニルインダン」という物質が深煎り=深焙煎になるほど多く含まれているらしく、摂取することでアルツハイマーやパーキンソン病につながる、アルミロイドという物質が脳にたまるのを防ぐ働きがあるそうです。
たぶん、それを更に深く実証するのはこれから、だと思いますが、現段階では中煎り=中焙煎よりも、深煎り=深焙煎のほうが、そのフェニルインダンが多く含まれていることはわかっている、ということですね。
そうか、すごいなぁコーヒーは。
だからといって中焙煎にその効用がまったくない、ということではないですので、じゃあ今日から俺はぜったい深煎りコーヒーや!深煎りコーヒーだけを飲むぞ!にならなくて大丈夫ですからね。
コーヒーにはいろんな効用がありますので、飲む事をまずは楽しんで、楽しんだ先にそうした効用がある、というほうが僕は楽しいと思ってます。
美味しく、そして楽しんで、その先に健康がある。
コーヒーで沢山笑顔になって、そして健康をキープして下さいね。
それでは、今日はゆかりんさんのツィート、それからライフハッカーさんの記事を参考に、ブログを書きました。(ありがとうございます!)
参考になれば嬉しいです。
それでは。
いつもありがとうございます。
焙煎アーティスト 島 規之
島 規之
最新記事 by 島 規之 (全て見る)
- 現在、店頭でのQR決済がご利用できません (5536) - 2026年2月24日
- あと一ヶ月すると (5535) - 2026年2月22日
- 簡単になったなぁ (5534) - 2026年2月21日
関連記事
-

-
フィルターによって挽き方は変えるの? (4719)
昨日はコーヒー生豆を仕入している商社の社長さんが、高槻店においでくださり、いろいろとお話する中で情報
-

-
あなたはどっち派!朝飲むコーヒー、夜飲むコーヒーのオススメは?
プロローグ 結構、聞かれる質問です。 朝に飲むコーヒー、夜に飲むコーヒーオススメはありますか?
-

-
コーヒー生豆配送の未来
今回はまぁ独り言なんですが、っていつも独り言か。笑 流通について、どうなるんだろって思っているんです
-

-
基本的に都度ブレンドしてます (5308)
昨日、月曜日に献血した時の血液検査の結果が届きました。 2日後には結果がウェブで見れる
-

-
どら焼きとコーヒーとわたし
こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です 先日 あるお客様に「どら焼きの美味しいお店っ
-

-
急冷にはキレがある (4988)
アイスコーヒーの本格的なシーズンインに。 アイスコーヒーの御質問が多くなってきておりま
-

-
島さんが一番好きな抽出器具はなんですか?
昨晩は家に早く帰れる日でしたので、高槻店が閉店時間にくるとささっと後片づけをして、富田にあるエビフラ
-

-
冷却器の掃除 (4647)
今週は焙煎機メンテナンスウィークの予定でしたが、ギフトのご注文が沢山あって月末に変更しました。 次の
-

-
月末ですが在庫はしっかりです (5151)
最近の月末はといいますと、来月の支払いを考えて出来る限り月末締めを超えるまでなんとかある在庫で乗り切
- PREV
- 好きはやっぱり最強だと思う
- NEXT
- 「美味しい」と感じるメカニズムを考える







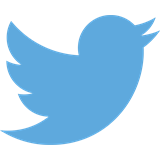






 RSSフィード
RSSフィード