大きくてもあかん 小さくてもあかん
昨日、何気なく聖飢魔Ⅱが目に入った。
デーモン閣下である。
小学生の時に、その歌声とメタルさに引き込まれて、カセットテープを何度も巻き戻してよく聞いたなぁ、なんて思いつつ、YouTubeで「ろう人形の館」を懐かしく聞いていました。
皆さんは、よく聞いていたアーティストって誰ですか?
僕はですね、筋肉少女帯、それからスターダストレビュー、尾崎豊、レベッカ、吉川晃司、布袋寅泰、とか洋楽も好き。
今でもステレオの前で、音楽を聴いている時間はほんとうに好きで、本を読みながら音楽に触れる時間を大事にしています。
この影響はやっぱり父からかな。
当時はレンタルレコードだったかな、親父がカセットに録音して、それを聞いてた。
オフコースとか、井上陽水とか。
レンタルビデオもよく借りてくれて、当時はシルベスター・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガーの映画が多かったかな、ランボーとかロッキーとか、ターミネーターとかプレデターとか。
ロボコップもあったなぁ、当時見た印象に残っている映画は、ベトナム戦争を題材にしたプラトーン。
こうして振り返ると、そうした音楽や映画に触れる機会を沢山作ってくれた、両親に感謝です。
懐かしいですよね。
こんにちは 焙煎アーティスト島規之です。
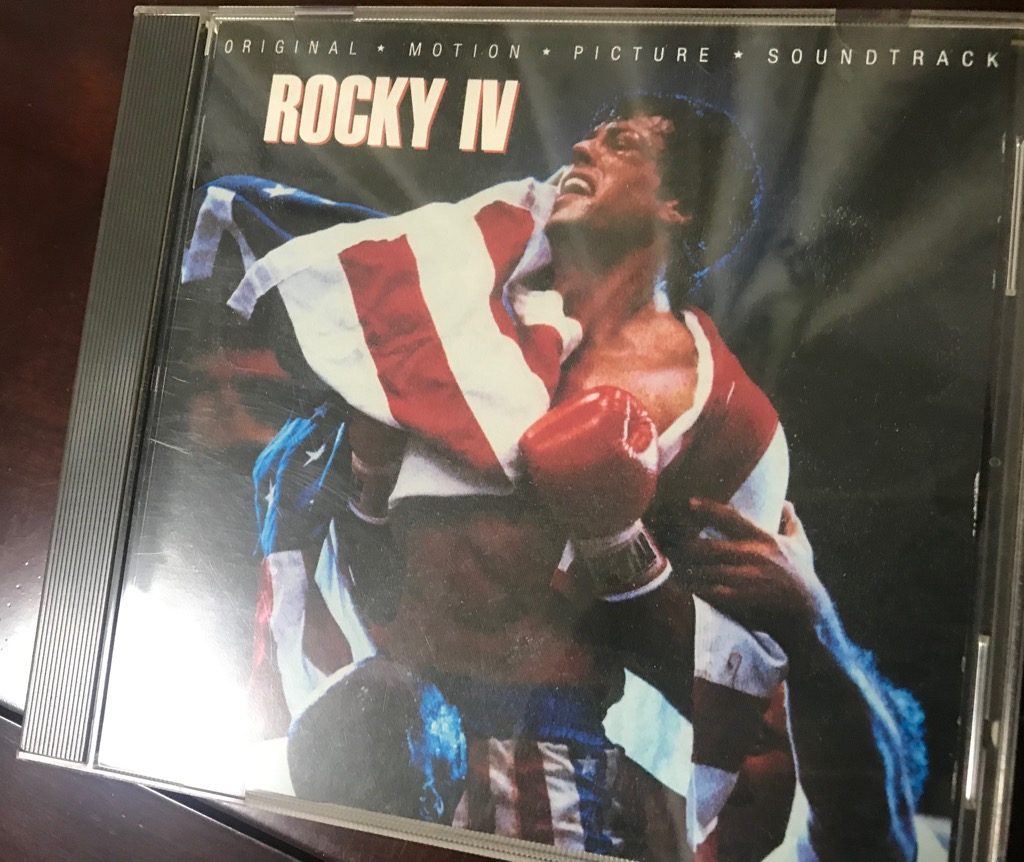
レコード進化論
聖飢魔Ⅱを聞いていて、なぜか家庭で聞く音楽の移り変わりをたどりだした。
レコードからCDへ。
あっというまだったような記憶があります。
そしてカセットテープも姿を消して。
曲をもう一度聞きたいときに、カセットテープを巻き戻すが、うまく曲の頭に巻き戻せない。
そうこうしているうちに、曲の頭に巻き戻せるラジカセができて。
そしてCDが現れ、レコードとカセットテープがCDにあっという間に追い越されていった。
そのあとMD、ミニディスクが現れた。
そのうちCDを凌駕するであろうと思われたが、そうはならなかった。
ここで思ったのが何でも小さくなればいい、というわけでもないんだ。
ということ。
そして、今、形のないダウンロードが主流になりつつあるように見えます。
大きいから小さいから、強いから素晴らしいから、残る、というわけでもない
ビデオテープもそう。
VHSとベータの覇権争い、がありましたね。
親父がいつもベータの方が何かつけて良い、とその性能の高さをよく教えてくれていましたが、結局一般になったのはVHSだった。
その時に性能がいいから、生き残れるというわけじゃないんだ、と思ったことを覚えています。
このデジタル機器などの変換の流れにおいて、時代に生き残っていくのは素晴らしいから、性能がいいからだけではない、と学んだわけです。
これを経営でも、ちゃんと理解しておかないとだめなぁなんて思っている次第です。
進化論でダーウィンはこう言っていました、強いものが生き残るのではなく、変化できるものが生き残ると。
そう、変化することに柔軟に。
聖飢魔Ⅱの「ろう人形の館」を聞いていて、なぜか進化論から生き残ることとは、を考えた、僕でした。
しかし、改めて振り返ると、ここ数十年の文明の進化はすごいね。
いつもありがとうございます。
焙煎アーティスト 島 規之
島 規之
最新記事 by 島 規之 (全て見る)
- 今期のブラジルは、よう伸びます (5521) - 2026年2月6日
- No.2 (5520) - 2026年2月5日
- 今年も高槻天神祭りが開催されると思います (5519) - 2026年2月4日
関連記事
-

-
ボクシングを見て 先読み力について考えた
こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です 年末に行われていた ボク
-

-
仕事がうまくいくコツとは
プロローグ 今日、お客様があって結婚したことのご報告を受けた。きゃーめでたい、きゃーめでたい、おめ
-

-
娘に教えた、速くなる走り方のコツ
実は僕、こう見えてってどう見えるのかは知りませんが(笑)、30歳を過ぎてからですが、70キロウルトラ
-

-
賢く振る舞おうとしない
本日はお休みですが、13時より高槻店の雨漏り修繕工事の打ち合わせがあり、高槻店へ行ってきます。 &n
-

-
コーヒー豆はぱくぱく食べられるのか?
プロローグ 今日は岡町本店からこんにちは 焙煎アーティスト 島規之です。 岡町本店はコーヒー
-

-
出版する本とか、ギフトの島珈琲カンとか、取材とか、島珈琲の近況報告
こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です。 さて、このブログを書いている今
-

-
ほんの少し幸せに ほんの少し豊かに
自営業をはじめ 独立したのが2002年 紆余曲折だらけですが13年目に入り 13周年も年が明ければも
-

-
より多くの体験 経験を積むには
こんにちは 焙煎アーティスト 島規之です これは僕がいつも思っているこ
-

-
コーヒーは心を豊かにする飲み物
最近 僕のテーマは「心を豊かにする」です こんにちは焙煎アーティスト 島規之です &n
-

-
今年出版する僕のコーヒー本
去年から動き出しました、僕のコーヒー本。 まえがき、第1章から第5章まで現
- PREV
- これは持ってて欲しい!とプロが思うコーヒー道具
- NEXT
- いつも同じ味わいを作り続ける、という努力






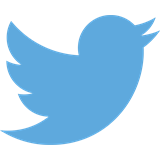






 RSSフィード
RSSフィード